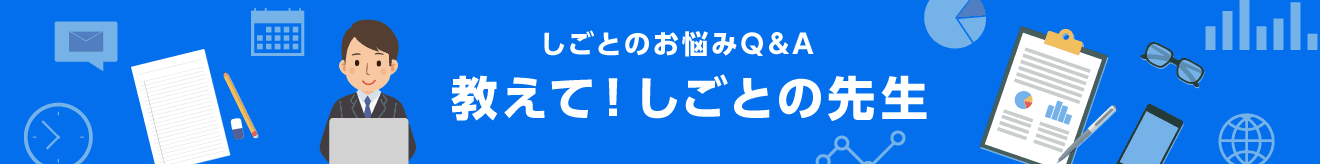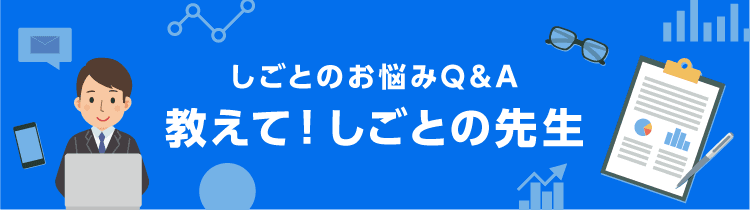回答(2件)
- ベストアンサー
「国鉄スワローズ」が消えて55年以上、公共企業体・日本国有鉄道の解体からも30年以上が経とうとしている今考えると、事実上の国営企業がどうしてプロ球団を持てたのか、本当に不思議に思いますが、国鉄球団は国鉄本体が直接の親会社ではなかったのです。 政府直営事業から、独立採算の公共企業体として1949年(昭和24)に発足した国鉄は、敗戦後の復員兵や海外引揚者の雇用の受け皿となったことで人員が膨れ上がり、9万5千人もの人員整理に着手したため労使関係が極度に悪化、この年有名な国鉄三大ミステリー事件(下山・松川・三鷹各事件)も起きます。当時の加賀山之雄・初代国鉄総裁は東京鉄道局の野球部長を務めたことのある大の野球好きで、労使間の緊張と混乱が続く国鉄職員の団結と意識高揚を目的にプロ野球参入を発案します。 国鉄の各地の鉄道局野球チームはノンプロの強豪で都市対抗野球の常連であり、野球を愛好する組織風土はあったとはいえ、事実上の国営企業のプロ参入など当時としても奇想天外なプランでした。 時あたかもプロ野球が2リーグに分裂した時期です。毎日新聞が結成する新球団を担いで多くの在阪私鉄球団がパ・リーグに行ってしまったため、残された読売=巨人主導のセ・リーグは球団数の確保に苦心、巨大組織国鉄をバックにする新球団の結成を支援します。こうしてほとんど冗談と思われていた国鉄球団のセ・リーグ参加が実現してしまいます。 しかし当時の日本国有鉄道法をどう拡大解釈しても、国鉄本体が副業としてプロ球団を経営することは不可能でした。 このため「交通新聞」を発行していた㈶交通協力会が中心となり、㈶鉄道弘済会(キヨスク経営など)・㈶日本交通公社(現JTBですが当時は国鉄傘下の小団体でした)など、国鉄の外郭団体が出資して設立されたのが、国鉄球団㈱です。 球団の出資者たる交通協力会などの外郭団体は、巨大組織国鉄の周縁の、ごく零細な事業者に過ぎません。 一応、実態上は総裁以下の国鉄本体が親会社らしく振舞い、球団への有形無形の支援もしましたが、当時は黒字経営だった国鉄本体からの金銭的な支援は、「球団後援会への援助金」という名目の間接的な福利厚生費のみで、それも球団存続期間を通じ年間700万円だけでした。現在とは物価水準が違うとは言え、当時も球団維持のためには微々たる金額でしかありません。 他の球団は「親会社の広告塔」として存在していて、親会社の連結決算対象の子会社である球団の赤字は、親会社の広告宣伝費として損金計上できる会計ルールになっていました。マスメディアは親会社名である球団名を連日報道してくれるのですから、球団の赤字など広告費と考えれば安いものでした、他球団の場合は。 しかし国鉄球団は赤字を親会社に補填してもらうこともできず、球団経営は常時苦しく、戦力の補強もままなりません。当時は黒字経営の巨大組織・国鉄がバックにいたとはいえ、内実は市民球団・広島カープにつぐ貧乏球団でした。 有望新人の獲得競争でも、契約金の提示合戦で他球団に必ず負けてしまうのでいい選手が集まらず、だから常にチーム力は弱体でBクラスが定位置でした。 球団の赤字を補填していたのは、「球団後援会からの援助金」です。入場料収入やグッズ販売など球団本来の事業収入とほぼ同額を、毎年後援会からの援助金で賄っていました。 球団後援会組織の中核は、当時約45万人いた国鉄職員です。強制ではなかったとはいえ国鉄職員の相当数が後援会に入っていました。 公共企業体・国鉄の歴史を通じ絶えず政治的対決を続けた当局と労組(国労など)も、唯一スワローズは一緒になって応援できる対象で、球団は「国鉄一家」の結束を確認するかすがいのような存在だったのは間違いありません。 この貧乏弱体チームにとって、名古屋の享栄商業を中退させて17歳で半ば強引に入団させた金田正一は最高の掘出し物でした。あまりに突出した存在ゆえに、他球団にも一般ファンにも、「国鉄スワローズ」イコール「金田のチーム」の印象が浸透します。金田自身も、監督もアゴで使うなどやりたい放題で「金田天皇」と呼ばれるチーム内のワンマンになりました。 しかし金田はその奔放な言動ゆえに多くのファンが彼を見るため球場に集まり、とりわけ金田が異常な闘志を燃やした巨人戦は注目されて、後楽園(当時は国鉄も巨人も本拠は後楽園)での巨人ー国鉄戦は、巨人ー阪神の伝統の一戦を上回る人気カードとなりました。 金田は球団にとって御しにくい存在ではありましたが、戦力的にも営業上も金田のいないスワローズなど成り立たなくなり、チームは貧乏球団ではありましたが彼に対してだけは出来る限りの給料で報いました。 金田も、国鉄の大家族主義的なユルい雰囲気を愛し、このような組織の中にいるから駄々っ子として振舞っても許されることを知っていたのです。 「400勝投手の金田正一さんの年俸は今で言うとマー君や菅野投手クラス(9億円)は払わないといけない価値です」 …その通りです。いや、400勝って年20勝を20年間続けないと達成できないとんでもない記録ですよ、今なら年俸20億円でもおかしくありません。 しかし、あの時代の野球選手の年俸って本当に低かったのです。貨幣価値が当時と現在で違うから絶対額が小さいのは当たり前なんですが、それにしても安すぎて当時の選手たちが気の毒に思えます。 こちらの二つのサイトに現役時代の、金田と、同時代の巨人の長嶋・王の年俸(推定)の年次推移が出ています。 https://www.youtube.com/watch?v=NJdHPX5JlpE http://net-kousien.com/nagashima-nenpou/ 金田は1957年(昭和32)入団8年目に1000万円プレイヤーになっていますが、国鉄在籍中の昭和30年代はほぼ年俸1千万円台で推移しています。1957年は28勝16敗で一人で貯金12を稼いだのに翌1958年は年俸1000万で据え置き。1958年は31勝14敗という今なら到底あり得ない数字にもかかわらず翌1959年の年俸は200万円上がっただけの1200万円。今なら「年俸3倍増」ぐらい要求して当然の成績です。 金田の国鉄最後のシーズンとなった1964年(昭和39)にようやく年俸2000万円に届きます。この年のライバルONの年俸は、前シーズン首位打者・打点王の二冠の長嶋選手が1400万円、2年連続本塁打王の王選手が初めて1000万円の大台に乗せました。 当時の貨幣価値を現在の貨幣価値に引き直すと、何をモノサシにするかで倍率が大きく違ってくるのですが、日銀のHPによれば1965年(昭和40)と2020年(令和2)の消費者物価指数は4.2倍で、まあざっと当時に比べて数字を4倍すればよい計算になります。 1964年当時の金田の年俸2000万円は、現在の貨幣価値で8000万円。長嶋は5600万円、王は4000万円となります。 …今の一流選手の年俸と比べて、あまりに低いレベルです。 今でこそ「職業に貴賤は無い」というのが社会常識として受け入れられていますが、当時は「いい大人が、野球などという児戯に類した遊びを仕事にして」という「賤業」意識が世間にも選手自身にも強くありました。野球でメシを食えるだけありがたいと思え、金額について四の五の言うな、というのが球団フロントの当然の理屈でした。 青空の下で溌剌プレーと明るい笑顔で少年ファンの憧れである長嶋や王が、給料の多い少ないで球団とゴネるなど夢を壊す話じゃないか、という社会からの無言の圧力もあって、長嶋や王は球団の提示額に毎年黙って一発更改していたそうです。 ONに比べれば、金田はかなりフロントと年俸を巡り揉めていた方で、あの通り口八丁手八丁な人でしたから交渉術も長けていたそうですが、何せ国鉄球団には金が無く、「長嶋より多く払っているから我慢してくれ」ということでサインしていたそうです。 1980年代に初の1億円プレーヤーとなった落合博満が連盟に日本人選手初の年俸調停に持ち込んで「球団提示に黙ってサインする」日本球界の悪弊に風穴を開けます。当時落合は「あの人たち(ONなど)が何も文句を言わなかったから野球選手の地位は低いままなのだ」と選手全体の年俸底上げのため自分は闘っていることを強調していました。 その後1990年代には代理人交渉制度も認められ、またトップ選手のメジャー移籍が当たり前になると、選手の年俸も「国際標準」になりましたが、昭和の時代の野球選手の年俸というのは今の基準で考えると不当なほど低く抑えられてきたのです。 金田の年俸は貧乏球団・国鉄にとって悩ましい問題で、彼に高額の年俸を拠出するために毎年資金不足で、他にいい選手を獲得できなかったというのは本当のようです。 とはいえ一人の野球選手に払える年俸の相場(当時の社会通念でそれは低いものでした)がありますから、どんなに毎年良い成績を挙げても他球団の選手と比しあまり突出した年俸を払うわけにもいかない。 「表向き」高い年俸を払えないため、球団も苦肉の策を打ったようです。年俸の代償として、有楽町の国鉄ガード下の営業権を与えると提案したこともあったとか(金田は断ったそう)。 また1958年(昭和33)に金田高義、1960年(昭和35)に金田星雄という金田の二人の実弟が投手として入団していますが、二人は幽霊部員ならぬ幽霊選手で試合出場実績はなく、実際は彼らの入団契約金を金田の給料の一部として払うのが目的でした(のち星雄は歌手としてそこそこの成功を収めました)。今なら考えられない話ですけれど。
< 質問に関する求人 >
ヤクルト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る